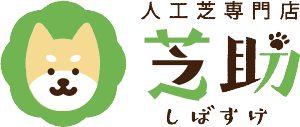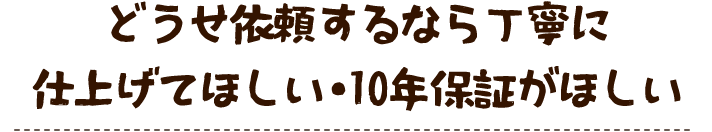コンクリートの上に人工芝を設置するには?敷き方の注意点や失敗しない方法を教えます!

「コンクリートの上に人工芝って敷けるの?」
「見た目は良さそうだけど、剥がれたり、ズレたりしない?」
「DIYか業者に任せるか悩んでいる…」
こうした不安をお持ちの方に向けて、施工実績1,000件超の人工芝専門業者「芝助」が、床材別の最適な敷き方・施工法・失敗しないための注意点をわかりやすく解説しています。DIYを検討している方にも、プロに依頼しようか迷っている方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
記事全体は以下のような構成で展開されています。
この記事でわかること
- コンクリートの上に人工芝は敷けます
- コンクリートの上に人工芝を敷くときの注意点
- コンクリートやベランダなど床材別の施工法
- 接着と重し、どちらを選ぶべき?
- 施工後に起こりやすいトラブルと注意点
コンクリートの上にも人工芝は敷けます!でも“やり方”には注意が必要です。
「コンクリートの上に人工芝って、敷けるの…?」
「滑ったり、カビが生えたりしないか心配…」
「人工芝って、ボンドで貼るの?それとも置くだけでいい?」
※(人工芝用接着剤を芝助では「ボンド」と呼んでいます)
DIYブームにより、バルコニー・屋上・駐車場など、コンクリートやアスファルトの上に人工芝を敷きたいと考える方は年々増えています。結論からお伝えすると、人工芝はコンクリートの上にも問題なく施工できます。
ただし、注意したいのは“敷き方次第で快適さも寿命も大きく変わる”という点。下地の種類や環境に合わない施工をしてしまうと、
- 剥がれて足元が危険!怪我につながることも…
- 雨水が抜けずカビやぬめりが発生…
- 接着剤の跡が取れず撤去が大変に
といった“よくある失敗”にもつながります。
コンクリートの上に人工芝を敷くときに知っておきたい注意点

① 静電気が発生しやすい
人工芝は化学繊維(ポリプロピレンやポリエチレンなど)で作られているため、摩擦や乾燥で静電気が発生しやすい素材です。特にコンクリートは電気を通しやすく、静電気が溜まりやすい傾向があります。
とくに安価な人工芝はリサイクル原料が多く使われており、静電気が起きやすくなります。一方で、バージン原料のみを使用した人工芝は、静電気が起きにくいという特徴があります。快適に使うなら、素材の質にも注目しましょう。
② 排水性に注意!水たまりやカビの原因になることも
コンクリートは水を吸収しないため、人工芝をそのまま敷くと水が溜まりやすくなります。中でも排水穴のない人工芝を使用してしまうと、雨のたびにぬかるみや湿気がこもり、カビや虫の発生につながる可能性があります。
水はけを改善するには、
- 裏面にしっかりと排水穴が空いた人工芝を選ぶ
- ゴミや落ち葉をこまめに掃除して通気性を保つ
- パイル(芝の毛)が素早く乾くポリプロピレン・ポリエチレン素材を選ぶ
といった工夫が大切です。
③ 表面温度の上昇に注意
人工芝は合成樹脂でできているため、夏場の直射日光で表面が非常に熱くなります。特にコンクリートの上は熱がこもりやすく、裸足で歩くとやけどするリスクも。
対策としては、日中は定期的に打ち水をしたり、シェードなどで影を作るのが効果的です。特に小さなお子さまやペットがいるご家庭では、安全性のために暑さ対策を行いましょう。
④賃貸は要注意! 接着剤の跡が残る可能性も
将来的に人工芝をはがしたいとき、ボンドで貼りつけた場合は跡が残ることがあります。アセトンなどの溶剤で落とすこともできますが、床材の種類によっては使用に注意が必要です。
心配な場合は、はがせるタイプの両面テープや片面テープ+ボンドで接着するなど、施工方法を選ぶことが大切です。
⑤ 固定は必須!ズレ防止のためにしっかり対策を
「人工芝は置くだけでOK」と思われがちですが、実際には固定をしないと風で飛ばされて、お隣の家を傷つけたり、めくれた部分に足を取られて転倒してしまう危険もあります。
お子さまが遊ぶ庭や、ペットと過ごすスペースには、安全のためにも両面テープやボンドなどでしっかりと固定する方法が推奨されます。
重し、両面テープ、片面テープなど、道具別人工芝の施工方法

コンクリートと一口に言っても、実はどんな床か、防水処理の有無によって人工芝の設置方法は異なります。ここでは、「重し施工」「両面テープ」「片面テープ+ボンド」「ボンドのみ」で施工する場合のそれぞれのメリット・注意点をご紹介します。
【1】重し施工

出典:amazon
メリット
プランターやブロックを乗せる重し施工のメリットは、跡がつかない事です。防水塗装の有無に関わらずコンクリート、長尺シート(主にバルコニーやベランダ、屋上などに最初から敷かれているゴムや、やわらかい床材のことを指します)に使用できます。

出典:amazon
中でも賃貸物件や現状復帰が必要な場合におすすめです。また、ボンドを使わないので、乾かす手間もなし。人工芝を設置したらすぐに、お子様もペットも遊べます。
注意点
手軽にDIYを楽しめる反面、人工芝が接着していないため台風や強風で吹き飛んだり、人工芝がズレて、滑って転んでしまう可能性も。そうならないために、しっかりと重さのあるもので、固定しましょう。
重し施工と相性の良い下地
コンクリート、コンクリート(防水塗装)、長尺シート、アスファルト
【2】両面テープ

出典:Amazon
メリット
人工芝を下地を同時に貼り付ける両面テープのメリットは、強度が強いこと。ある程度しっかりと固定できます。防水塗装の有無に関わらずコンクリート、長尺シートに使用可能です。
ただし、両面テープは水分やホコリがあると接着力が発揮しにくいため、下地が乾いた晴れの日に施工がおすすめです。また、テープを使用する場合は水の逃げ道を作るのがおすすめ。周囲を全部囲ってしまうと、水が逃げれないので、水はけも意識してDIYしましょう。
デメリット
しっかりと固定される反面、、将来的に剥がす際は跡が残る可能性があります。原状回復を考えている場合は要検討です。
両面テープと相性の良い下地(現状復帰をしない場合)
コンクリート、コンクリート(防水塗装)、長尺シート、アスファルト
【3】片面テープ+ボンド

出典:Amazon
メリット
特別風が強かったり、直射日光がかなり当たる場所では片面テープとボンドを使って設置すると安心です。テープの粘着のない部分にボンドを塗布して貼り付けていきます。ちなみに芝助でも採用している最近人気の施工方法です。
デメリット
ボンドを使用するため、剥がすのが大変です。また、跡が残る可能性も高いため、賃貸住宅の方はご注意ください。
両面テープと相性の良い下地(現状復帰をしない場合)
コンクリート、コンクリート(防水塗装)、長尺シート、アスファルト
【4】ボンド

出典:Amazon
メリット
ボンドのメリットはなんと言っても接着力の強さです。重し施工、片面テープ、片面テープ+ボンドと比較しても強度は群を抜いています。
デメリット
防水塗装されているコンクリートで、ボンドを使用すると、見栄えが悪くなったり、防水塗装を痛めるので注意が必要です。また、剥がすときに跡が残るので現状復帰をお考えの方はおすすめできません。
両面テープと相性の良い下地(現状復帰をしない場合)
コンクリート、アスファルト
結局、接着と重しどちらを選ぶべき?

ここまで、重し、両面テープ、片面テープ+ボンド、ボンドのみをご紹介してきました。
しかし実際に設置する際、「接着か、重しか?」と迷われる方も多いのではないでしょうか?どちらを選ぶかは、床の材質や使用目的、原状回復の必要性によって変わります。
以下では、それぞれの方法のメリット・デメリットと選び方のポイントを、芝助の実際の施工現場の視点から詳しく解説します。
1. しっかり固定したいなら「接着」
人工芝をしっかり固定したい場合や、人の出入りが多い場所、ペットやお子さんが走り回るスペースには、ボンドや両面テープによる接着施工がおすすめです。
メリット
-
芝がズレにくく、安全性がたかいため、子どもが走り回っても安心
-
強風や台風の際も飛ばされにくい
デメリット
-
剥がすときに跡が残ることがある
-
床材によっては施工不可(防水加工や長尺シート等)
特に賃貸住宅や将来的に人工芝を撤去する予定がある場合は、跡残りリスクの少ない施工方法を選ぶ必要があります。
2. 手軽さと原状復帰を優先したいなら「重し」
「将来的に撤去するかも」「接着剤を使いたくない」そんな方には、プランター、植木鉢、レンガやブロックなどの重しを利用した重し設置が向いています。
メリット
- 人工芝そのものにも重さがあるため、何も置かなくてもそう簡単には吹き飛ばない
- 接着剤を使わないため、原状復帰が簡単
- 防水コンクリートや長尺シートにも対応しやすい
デメリット
-
強風でめくれる可能性がある
-
使用環境によってはズレやすい
特に防水塗装された床や長尺シートの上では、ボンドの使用が難しいため、重しを使った設置方法を選ぶのが安心です。
コンクリートに人工芝施工後に起こりやすいトラブルと注意点

① 強風で人工芝がめくれたり飛ばされる
原因
固定が甘い、重し不足、テープの劣化
対策
-
両面テープや片面テープ+ボンドでしっかり接着
-
角や端に重し(プランター・レンガ)を配置
-
台風前は一時的に片付ける
② 排水がうまくいかず、水たまりやカビが発生
原因
排水穴のない人工芝 or 水はけの悪い下地
対策
-
排水穴つきの人工芝を選ぶ
-
定期的に落ち葉やゴミを取り除く(ブロワーや竹ぼうき活用)
-
梅雨や雨の多い季節は風通しをよく
③ 人工芝のズレや浮き上がり
原因
テープが湿気で剥がれる、重し不足
対策
-
湿気に強い人工芝用テープを使用
-
テープが効かない床(防水など)では「重し施工」+家具で固定
④ 静電気の発生
原因
化学繊維の芝×乾燥した空気(冬・室内)
対策
-
バージン原料の人工芝を選ぶ(静電気が起きにくい)
-
定期的に水を撒いたり、静電気防止スプレーを使う
接着剤の跡が残って原状回復が大変
原因
強力なボンドの使用
対策
-
剥がしたい予定があるなら「両面テープのみ施工」がおすすめ
-
剥がす際は、FRPアセトン等を目立たない場所でテストしてから使用
-
長尺シート・防水床にはそもそも接着しない方が無難
このようなトラブルを防ぐためにも、事前の床チェックと施工法の選択がとっても大切です。
「コンクリートを人工芝にしたい!でもちょっと不安…」そんなときはプロに相談するのが安心です
コンクリートやベランダなど、平らに見える床も素材や状態によって施工方法が変わるため、「本当にこの方法で合ってるのかな?」「DIYで失敗したくないな…」と感じる方も多いはず。
そんなときは、人工芝専門業者にぜひご相談ください。お庭やベランダの状態を確認したうえで、あなたのライフスタイルや目的に合った施工方法をご提案いたします。
芝助の施工なら、コンクリート上でも安心・きれい・長持ち!

人工芝のプロである芝助では、床の種類や用途に合わせて、最適な施工方法を選んでいます。お客様の使い方や、将来の撤去のしやすさまで考慮して、後悔のないご提案をお届けしています。
芝助の最近の施工では、強力な片面テープ+ボンドのハイブリッド施工を採用するケースも多数あります。一部だけ剥がしたい、という場合にも対応しやすい工夫をしています。
「うちはどれが合ってるの?」「できれば接着跡は残したくない…」そんな細かなご要望も、施工1,000件超の芝助が現地を見てベストな提案をいたします!ぜひお気軽にご相談ください。